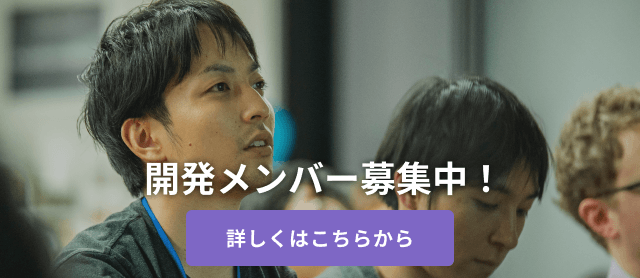この記事はヌーラボブログリレー2025夏の12日目として投稿しています。
こんにちは。RevOps部データインテグレーション課のSamです。2024年にインハウスシステム課がまるっとみんな一緒に異動になりまして、RevOps(Revenue Operation)を推進するチームの所属になりました。私達のチームはデータ統合基盤を保有していますので元々データ分析をしてはいたのですが、この組織改編により、分析結果が以前より素早く経営層まで届く様になりました。
ですが、同時に新たなミッションが「今日からこっちでお世話になります!ヨロシク!」みたいな威勢の良さでやってきました。
目次
え、もう「今期の着地」ですか!?
さて、発足からそう時を置かずしてとある質問が来るようになりました。
「今期の着地っていくらになる?」
これです。「今期の着地」とは、今期の業績や活動が最終的にどのような結果になるかの予測値の事です。期首に設定する目標値とは違います。目標値に対して実績や予定を踏まえて「実際のところ達成は無理そう?それとも余裕そう?」を測るための数字と言ったらわかりやすいでしょうか。これを発足早々に問われた訳です。それも、まだ「今期」が始まる前に……。
「それ、来期では?」というツッコミは置いておいて、早い話が「今」の予測を「素早く」出してくれというオーダーです。
「え、もう!?」という驚きはありました。ですが、新部署である「データインテグレーション課”なら”どう出す?」との問いです。やるしかありません。当社の経営管理が、次の段階へと進んでいる証しだと受け取り、まずは整理することにしました。
(以降、SaaSビジネスにおける売上予測の一般的な考え方について、当社の実務上の詳細な運用とは切り離して、普遍的な知見として解説します)
明日の事すら「確実」ではありませんけども
まず、大前提としてひとつ言えるのは、「正確な未来の数字は誰にもわからない。」です。
それは、データとして現れているものは所詮「結果」の数字であり「過去のもの」だからです。そこに確定未来はありません。昨日お試ししてくれたユーザー数はわかります。でも、そのうち何人が明日になった時に「絶対」正式契約してくれるかなんてわかりません。更には契約したとしてもその全員が「絶対」キャンセルしないとは限りません。いつかはします。それは1年後、5年後かもしれませんし、クレジットカードの有効期限が切れてて即日キャンセルなんて事態にならないとも限りません。
でも、逆に全くわからないわけではありません。
「お試ししてくれたユーザーのX割くらいが契約してくれた」などの過去の実績はあるわけですから、「X人くらいは正式契約してくれる……んじゃないかなぁ?」という予測はできます。「可能性が高い数字」なら示せるわけです。
ですが、それであっても不確定な数字を知る事に意味はあるのでしょうか?期末が近づけばより正確な数字を出せるでしょうが、未来の数字であればあるほど不確定になります。
取らぬ狸の皮算用と言うではないですか。来年の話をすると鬼が笑うわけですよ。
「ねぇ、完璧じゃないものでも本当に要るの?使うの?ピタリ賞なんて無理ですよ?」
と及び腰になるのは仕方がないと思うのです。
ですが、結論としては、「要る」のです。
そしてそれは、正確な「確定未来の数字」でなくとも十分なのです。
何故かって?その理由には、売り切り型のビジネスとは違う、サブスクリプション方式ならではの特性が関係しています。
買い切り型とサブスクリプション方式との違い
SaaS企業の売上は積み上げである
CDなどの物品の売買のように、一度料金を支払うことでそのCD自体と収録されているコンテンツ(音楽など)を利用する権利を得るのを買い切り型といいます。それに対して、SaaS(Software as a Service)のサービスはサブスクリプション方式での売買がメインです。サブスクリプション方式とは、月額や年額などの定期的な利用料を支払う形で提供されることが多く、必要な期間だけ利用できるというものです。
この2つの方式で1年間で78万円の売上を上げるケースを例にして比較してみましょう。
買い切り型の商品の場合、売上は売った月での売上になります。そのため年間78万円を達成するためには、平均的に毎月6.5万円分商品を売る必要があります。商品が一つ5千円だったとすると、毎月13個売るペースです。
 年間78万円を達成するには、買い切り型だと毎月平均6.5万円の新規契約が必要となる
年間78万円を達成するには、買い切り型だと毎月平均6.5万円の新規契約が必要となる
ではサブスクリプション方式だとどうなるでしょう。同じく1年間で78万円の売上を上げるケースで考えてみます。
例えば(少々高額ですが)月額5千円の音楽配信サービスなどでイメージしてみてください。この場合一度契約をしたら解約するまで毎月支払いが発生します。 そのため、毎月新規契約を2件取れば年間78万円を達成できるのです。もちろん実際は解約もありうるので新規だけで考えるべきではないのですが、話を簡単にするために、「新規=契約数の増加数」として考えていきます。
*注記:買い切り型との比較をわかりやすくするため、解約はされない前提としています。
 年間売上78万円を達成するには、サブスクリプション方式だと毎月1万円分の新規契約を獲得すれば達成できる。
年間売上78万円を達成するには、サブスクリプション方式だと毎月1万円分の新規契約を獲得すれば達成できる。
SaaSにおける「契約タイミング」の重要性
先程の例のサブスクリプション方式であれば、4月に倍の4件の新規契約をとった場合、10月、11月、12月、1月で新規を全く取れなかったとしても年間78万円を達成できます。素敵ですね。期首に売れれば売れるほど左団扇でいれるということです。
 サブスクリプション方式の場合、期首に予定より1万円多く新規契約を獲得した場合、10月から1月まで1件も新規契約を獲得できなくても年間売上金額が毎月1万円の新規契約を獲得したときと変わらない
サブスクリプション方式の場合、期首に予定より1万円多く新規契約を獲得した場合、10月から1月まで1件も新規契約を獲得できなくても年間売上金額が毎月1万円の新規契約を獲得したときと変わらない
サブスクリプションって楽そうでいいなと思うかもしれません。ところが、6月の新規契約が全く取れなかったケースを考えるとそうも言ってられません。
買い切りの場合、6月の6.5万円が無くなるだけなので年間の売上は71.5万円です。
 買い切り型で6月分の新規契約が1件もなかった場合、年間売り上げ金額は71.5 万円となる。
買い切り型で6月分の新規契約が1件もなかった場合、年間売り上げ金額は71.5 万円となる。
ところが、サブスクリプション方式の場合、6月に取れなかった1万円が翌年3月までの10ヶ月間失われるということですので年間10万円の損失となり、年間の売上は68万円となってしまいます。買い切り型よりダメージが大きいです。
 サブスクリプション方式で6月に新規契約を1件も取れなかった場合、年間10万円分の売り上げを失い、年間売上金額は68万円となる。
サブスクリプション方式で6月に新規契約を1件も取れなかった場合、年間10万円分の売り上げを失い、年間売上金額は68万円となる。
取り戻しの難しさとリカバリー戦略での速度効果
先程の例で6月に失注した1万円の新規契約は年間でいうと10万円の価値がありました。この10万円の損失分を年内にリカバリーしようとしたら、どこかの月で+1万円新規を増やせばいいかというとそういうわけにはいきません。
11月にリカバリーしようとしたら、+2万円分(合計3万円)の新規契約を取らないと失った10万円を取り戻せません。5千円のサービスですから6件の新規契約が必要です。
 6月に1万円分の新規契約を取れなかった場合に失った年間10万円の損失を、11月の新規契約分で取り戻そうとすると11月に2万円多く(合計3万円)の新規契約を取得しなければならない。
6月に1万円分の新規契約を取れなかった場合に失った年間10万円の損失を、11月の新規契約分で取り戻そうとすると11月に2万円多く(合計3万円)の新規契約を取得しなければならない。
まして、2月にリカバリーしようとしたら+5万円分(合計6万円)の新規契約を取らないと年額10万円分を回復できないのです。5千円のサービスですから6月だったら2件でよかったのに、2月だと12件も取らないといけません。つまり、リカバリータイミングが後になればなるほど月の達成目標が上がります。しんどいですよね。
 6月に1万円分の新規契約を取れなかった場合に失った年間10万円の損失を、2月の新規契約分で取り戻そうとすると2月に5万円多く(合計6万円)の新規契約を取得しなければならない。
6月に1万円分の新規契約を取れなかった場合に失った年間10万円の損失を、2月の新規契約分で取り戻そうとすると2月に5万円多く(合計6万円)の新規契約を取得しなければならない。
“予測”は未来を当てるためじゃなく、行動を早めるためにある
会社というのは基本的に年間売上の予定を立てているものです。それを月単位に落として、売上予算としているところが多いのではないでしょうか。
もし、売り切り型のサービスであれば、失った金額と同額の金額をどこかの月で売り上げれば挽回できます。11月でも2月でも、挽回すべき金額は変わりません。
「今月までの売上実績額合計-今月までの予算額合計」がマイナスであれば、その金額が来月以降のどこかに追加するべき目標金額です。
ところがサブスクリプション方式の場合、どの月にマイナスになったか、そしてどの月で取り戻すのかによって上記のように月毎の取り戻すべき金額が変わってしまいます。
だからこそ売上予測が大切なのです。年額10万円の損失を6月に気がつけば6件÷2件=3倍頑張ればいいとして、11月に漸く気がついた場合12件÷2件=6倍頑張る必要があるのです。6倍なんて、諦めたくなるかもしれません。ですから、できるだけ早く目標との差を知ることが大切なのです。
ちなみに、今売上目標を余裕で超えそうなら、明日の売上を考えるより未来への投資に早めに力を入れるという判断もできます。マイナスな予測もプラスな予測も、どちらも大切なのです。
完璧よりシンプル&ブレの少ない予測を
将来の売上・業績を予測し、その情報を元に計画を立てるプロセスをフォーキャストマネジメントと言います。*1このときに必要なのは、「1円単位でピタリと当たる予測」ではありません。重要なのは、戦略判断に使えるレベルで信頼できる予測です。
会社の正式な売上金額は財務会計(「会計の基礎知識」*2を参照)の数字です。この数字を元に社外の利害関係者が経営状態を判断するのですから、どんぶり勘定で許されるわけがなく、緻密な調整はどうしても入ります。財務会計の最終的な売上金額は、通貨レートや期間按分、調整金など多くの要素を反映して決まります。これらをすべて見越して1円単位で一致させる予測を作ろうとすれば、計算は複雑になりすぎますし、現実的には不可能です。
だからといって「適当でいい」というわけでもありません。予測の精度は、会社の規模や事業フェーズによって異なりますが、一般的に誤差が±10%程度に収まっていれば、重要な経営判断の基礎として役立つケースは多いのではないでしょうか。例えば「100件売れる」という予測であれば、90〜110件の範囲内であればOKという感覚です。この“ブレ幅”を前提に、戦略やリスクヘッジを組み込むことが重要です。
もちろん、売上規模が大きくなると10%でも大きな金額になります。たとえば1億円の10%は1千万円です。ですから、できるだけブレ幅を小さくする努力は必要です。しかし、それは「完璧を目指す」ことではなく、「最大でもX%程度の誤差に抑えられる」予測を作ることです。
予測精度が高まることで、より一層、意思決定に耐えうるものとなり、経営のスピーディなアクションに繋げられると思います。
ざっくりだけど行動につながる数字を早く出すには?
実際に売上予測を立てるとしたらどうするのがいいかと言いますと、財務会計の数字ではなく「管理会計」の数字を使うことをお勧めします。
MRRという単語で調べてもらうと計算方法がでてくると思います。この時、思い切って為替レートやら調整金額やら日割りやらには目を瞑って「契約件数✖️単価」のレベルの計算式で作ってしまうのがお勧めです。そうすることで、売上の増減に対する要因が新規契約数なのか解約数なのか、アップグレード数なのかダウングレード数なのかなどの分解がしやすいからです。その上で、財務会計の値に対する精度を一定値以下に押さえておけば、十分その予測は使えます。
もちろん、財務会計の数字を使って単回帰分析を行って回帰直線を描いて売上予測を出すという方法もあります。お手元の表計算ツールに「FORECAST関数」などがあればそれが使いやすいでしょう。
ただ、この方法は過去の実績に大いに引っ張られますし、売上の要因分析はできません。例えば過去の実績の中に、「たまたまその年だからできたこと」が含まれてしまった場合に数字がミスリードされます。過去の実績が毎年繰り返されるという前提で考えることはリスクに繋がるのです。更に、「過去にできなかったこと」を予測に加えることもできませんん。売上向上のために例年やっていなかった様な施策を考えていて、その場合の予想を出したいという場合にも使えないのです。
他にも色々と方法はあるでしょうが、サブスクリプション方式は早く予測を出し、戦略を立て、早く動くのが鍵です。そしてそれは正確な「確定未来の数字」でなくとも十分なのですから、仕組みがシンプルな管理会計の数字で算出するのがお薦めなのです。
まとめ
ここまでのお話をぎゅっとまとめると、こんな感じです。
- 売上予測の目的は「未来をピタリと当てること」ではない
→ 大事なのは「早く気づいて、早く動く」ための目安をつくること。 - 完璧な精度は必要ありません
→ ±10%程度の“ざっくり感”でも、売上予測の第一歩として価値があります。 - SaaS型ビジネスでは“早さ”が命
→ 期初に積み上げられた契約は解約されない限りずっと効きますが、リカバリーが遅れるほど挽回が難しくなります。 - 数字は行動のためのツール
→ 予測は安心材料ではなく、次の一手を考えるためのもの。 - 売上予測は管理会計の数字で行うとシンプル
→MRRの計算式を構成する各変数の数字を予測して計算して出すとシンプルで使いやすい。
あとがき
「売上予測を出すなんて、難しそうだし外れたらカッコ悪いから嫌だな……」なんて感じていませんか?躊躇してしまう感覚はわかります。でも安心してください。繰り返しになりますが、ざっくりで良いんです。売上予測の目的は「早く気づいて、次の手を打つこと」であり、「今の状況や計画のままだとどうなるか」を知らせるのがその役割なのですから。
そうして、いざ予測をしようとあなたが一歩踏み出した時、もしかしたら「早く!」と急かしてくる人が現れるかもしれません。もしかしたらその時相手の勢いに驚くかもしれませんが、そんな時はSaaSの売上の仕組みを思い出してください。その方が「とびきりせっかちさんな人」という訳ではなく、売上の仕組み上「早さ」がそのまま価値になるからだということを思い出せば、納得できることでしょう。寧ろ、「今すぐ!」と動いてくれる人がいることが、実は会社の売上を守る一番の近道だったりします。
勿論、売上予測を秒で作れる訳ではないので、そこはご理解いただく必要があります。とはいえ早く作るのはとても価値があるので、まずは第一弾を作り、徐々に改修を加えていくといいでしょう。きっと「早く!」と言ってくれる方が、予測の改修ポイントのヒントをくれる筈です。
最後になりましたが、売上予測をすることで、時間を味方にしたみなさんのプロダクトが今後益々発展していくことを願っています。
敬具
*1:川上 エリカ; 丸井 達郎; 廣崎 依久. 「レベニューオペレーション(RevOps)の教科書 部門間のデータ連携を図り収益を最大化する米国発の新常識(MarkeZine BOOKS)」より
*2:https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/financial-accounting/