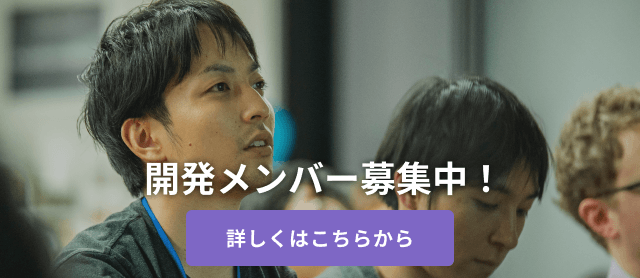2025年5月21日、ヌーラボは全社オフラインハッカソン「Nulab AI Agent Hackathon: Sparking Innovation」を開催しました。このイベントは、全エンジニアがAIエージェント技術に集中的に取り組み、「未来の働き方」の創造に向けた重要な第一歩を踏み出す一日となりました。本記事では、その熱気あふれるハッカソンの体験をレポートします。
目次
はじめに
このブログ記事の目的は、ヌーラボで開催したAIエージェントハッカソンの貴重な体験を皆さんと共有することです。
イベントの正式名称は「Nulab AI Agent Hackathon: Sparking Innovation」。2025年5月21日(水)の9時から19時まで、ヌーラボ福岡オフィスの6Fと7F、そしてTKPガーデンシティを会場として開催しました。
この日は、ヌーラボのほぼ全てのエンジニアが参加し、AI技術と真剣に向き合った、ヌーラボにとってSparkingな一日となりました。
なぜ今、AIハッカソンなのか?
今期におけるヌーラボの重要な全社目標の一つとして、AI活用を全社的に加速させることを掲げています。本ハッカソンは、この目標達成に向けた大切なキックオフとして位置づけています。AIエージェント技術は、私たちの働き方やプロダクト開発のあり方を根本から変える大きな可能性を秘めていると、私たちは考えています。
このイベントには、以下のような目的とねらいがありました。
- AIエージェントを開発プロセスに組み込む体験をする。
- AIを使ったサービスのアイデアを考えて実装できるようになる。
- チーム外とのコラボレーションを通じて視野を広げ、協業しやすくなる。
- 自身のスキルを飛躍的に向上させる。
- 新たなアイデアを生み出す刺激的な体験をする。
- ヌーラボのプロダクトや働き方を自らの手で進化させる。
イベント名である「Sparking Innovation」には、AI時代の新しい「はたらく」を私たち自身の手で創造していく、という強い想いを込めています。
ハッカソンへの「事前準備」
参加対象は、原則としてヌーラボの全エンジニアとしました。非エンジニアの参加者については、Difyの活用を推奨しました。
重要なルールとして、ハッカソン当日の1日で開発をやり切るため、事前の本格的なコーディングは禁止しました。これは、公平性の確保や、ハッカソンならではのライブ感を重視したためです。
一方で、当日の時間を最大限に活用できるよう、「事前準備」を積極的に推奨しました。具体的には、以下のような準備を挙げます。
- アイデアの具体化・深掘り: 開発する機能、ユーザーシナリオ、目標の明確化。Cacooでの構成図・画面イメージ作成。
- 技術調査・学習: 利用ツールの調査・学習(AIエージェント、API、ライブラリなど)。
- 設計・役割分担: システム構成検討、当日の役割分担相談。
- 開発環境の準備: ソフトウェアインストール、アカウント作成、APIキー取得、簡単な動作確認。
参加者の挑戦をサポートするため、複数のワークショップやアイデアソンといった事前学習の機会も設けました。
- AIエージェント活用開発講座
- Difyによる業務改善ハンズオン
- プロンプトエンジニアリング講座
- アイデアソン
ハッカソンで利用可能だった主な技術環境は以下の通りです。
- Amazon Bedrock (Claude): ハッカソン専用のAWSアカウント上に構築し、参加者には限定的なアクセス権を付与しました。Bedrock上のanthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0モデルをハッカソン指定モデルとして提供しました。
- Vertex AI (Gemini): gemini-2.5-pro-preview-05-06 / gemini-2.5-flash-preview-05-20モデルが利用可能でした。
- Cline: AI開発アシスタントを行うVS Code拡張。Bedrock (Claude) および Vertex AI (Gemini) の環境セットアップガイドも事前に共有しました。
- Gemini for Google Workspace: 社内のGoogle Workspace環境で利用可能なGemini。
- Dify: ノーコード・ローコードでAIアプリケーションを構築できるプラットフォーム。
- OpenAI: OpenAIが提供する各種AIモデルへのアクセス。
熱狂の開発タイム! (ハッカソン当日)
当日はオープニングの後、午前と午後に分けて開発タイムを設け、間にランチ休憩を挟むスケジュールで進行しました。
チーム編成は、原則として3〜4名(Difyチームは2〜3名)のランダム編成で行いました。これにより、普段なかなか関わることのないヌーラバー同士が協働する機会が生まれ、新たな化学反応が期待されました。
開発テーマは、以下の領域から選択するか、あるいは自由に設定することが可能でした。
- 開発プロセス改善
- Nulabプロダクト進化
- DX、業務ハック
- 自由テーマ
開発中の会場は、限られた時間の中で各チームがアイデアを形にしようと集中する熱気に包まれていました。多くのチームがAIエージェント(主にCline経由でBedrockやVertex AI)を積極的に活用し、AIを文字通り「共同開発者」として捉え、開発を進める試みを目の当たりにしました。もちろん、技術的な課題に直面する場面もありましたが、メンターやチームメンバーと協力し合いながら、それらを乗り越えていきました。
私たちのチームは、普段は経営やマネジメントを主業務とするCEO、CTO、そして部長陣という、エンジニアリング業務から少し離れたメンバー構成でこのハッカソンに臨みました。AIエージェントと真剣に向き合うというテーマのもと、全員で「Cline」「Dify」を駆使したコーディングに挑戦。最初は手探り状態でしたが、AIと対話しながらコードを生成・修正していく新しい開発スタイルを体験し、試行錯誤の末、アイデアを形にし、作品を完成させることができました。開発プロセスにおいては、コーディングだけでなくプロジェクトマネジメントの面でもAIの力を大いに活用しました。具体的には、Geminiに短時間のプロジェクトを成功させるためのクリティカルパスの洗い出しといったプロジェクトマネージャーのような役割を担ってもらい、限られた時間の中で効率的に開発を進めることができました。まさにAIと共創しながら、普段とは異なる立場のメンバーが一丸となって開発に取り組んだ、刺激的な体験となりました。
創造性の祭典! (成果発表会)
総勢25チームが参加した今回のハッカソン。その成果を発表する「創造性の祭典」は、各チーム持ち時間3分のライトニングトーク形式で行われました。動くデモを中心に据え、Cacooなども効果的に活用しながら、開発した成果の魅力や可能性を伝えました。
評価は、以下の4つの観点で行いました。
- 開発プロセスAI活用度 (30%)
- アイデア・アイデアのAI活用度 (30%)
- 技術力 (20%)
- デモ/発表 (20%)
審査員による採点(最優秀賞)と、参加者全員による投票(オーディエンス賞)によって、各賞を決定しました。短時間で非常に多様なアイデアが実現され、発表される様子は圧巻で、参加者にとって刺激的な時間となりました。
今回のハッカソンでは、AIエージェント技術を活用した多種多様な作品が生まれました。特に目立ったのは、BacklogやSlackといった既存の業務ツールとの連携を深め、日々の業務を効率化するアイデアです。例えば、Slackの会話をAIが要約してBacklogに課題登録する「Slack要約コンニャク」、コミット情報からプルリクエスト概要を自動生成する「レミング」、Backlogのタスク進捗やSlackでの議論をAIがモニタリングする「Nulab-Pulse」などが提案されました。
また、コミュニケーションを円滑にするためのユニークな試みも見られました。社員データから独自のロジックでSmall Talkの相手を提案する「波動共鳴」、Backlogの活動から絵日記を生成する「Backlog絵日記」、チームの「気配」を絵文字で共有する「たゆたいLog」など、AIを介して人と人との繋がりをサポートする作品が登場しました。
開発プロセスそのものを改善する提案も活発で、AIがプロジェクト概要からタスクを自動生成する「Backlog Composer」、Cacooでの作図をAI猫ミームがサポートする「cat_meme_asistant」、プレゼン資料と音声からAIが審査を行う「Judge AI」など、企画から評価に至るまでの各フェーズでAIを活用するアイデアが発表されました。
その他にも、音声入力でBacklogに課題登録する「うっほ!うっほほ!しゃべってタスク」、チャットベースのオンボーディング支援ツール「NuGuide」、PM業務を体験できるシミュレーションゲーム「NuPM」、社内情報をRAGで検索できる「ヌーラボ迷子センター」、AIによる文章校正ツールなど、Nulabプロダクトの進化やDX、業務ハックに繋がる幅広い分野でのAI活用が試みられました。これらの作品群は、AIエージェントが日常業務やプロダクト開発に革新をもたらす可能性を具体的に示していました。
栄光そして未来へ (結果発表・表彰、そしてこれから)
厳正なる審査の結果、ハッカソンの成果が称えられ、以下の賞が贈られました。
- 最優秀賞 (Grand Prize): チーム「クアッカワラビー」による「Backlog Composer」。AIを活用してプロジェクト概要からタスクを自動生成し、Backlog初心者のオンボーディングを支援するツールです。
- オーディエンス賞 (Audience Choice): チーム「cat_meme_asistant」による「cat_meme_assistant」。Cacooでの作図作業をAI猫ミームが楽しくサポートするブラウザ拡張機能です。
ハッカソン終了後には、任意参加の懇親会を開催し、軽食とドリンクを片手に、参加者同士が互いの健闘を称え合いました。各チーム、本気で開発に取り組んだからこそ、結果発表では悔しさをにじませる場面や、「もっとこうすれば良かった」「次はこうしたい」と熱心に振り返る声も多く聞かれ、その真剣さが非常に印象的でした。
このハッカソンは、ヌーラボ全体のAI活用を加速させるための、非常に大切なキックオフイベントとなりました。参加者一人ひとりが、AIエージェントと真剣に「向き合った」この日の経験を通じて、今後の業務や「未来の働き方」の創造に向けた大きな学びと、そして新たな意欲を得ることができたと確信しています。
参加者の声(アンケートより抜粋)
実際に参加したヌーラバーからは、多くの熱い感想が寄せられました。
AIの可能性や楽しさを改めて実感し、「AIをどう生かすか学べた」「AIエージェントとハッカソンの相性が良い」といった声が多く聞かれました。また、開発プロセスそのものを楽しんだり、チームでのコラボレーションから新たな学びを得たりと、「どのチームも動くものが開発できており非常に良かった」「普段の業務にもこの集中力を取り入れたい」といった意見も印象的です。
当初は参加に不安があったものの、「チームでアイデアを出し始めたら面白くなった」「全員参加で良い体験になった」と感じた人も多く、今後のAI活用への積極的な姿勢や、さらなるハッカソン開催への期待の声も上がりました。
一方で、「AIの期待する結果を得る難しさ」「AIレスポンスの責任所在の明確化」といったAI活用における課題も寄せられました。これらの貴重な意見は、今後の取り組みに活かしていきます。
そして何よりも、「運営ありがとうございました!」「非常に楽しかったです!」といった運営チームへの温かい感謝の言葉が多数寄せられたことが、今回のハッカソンの成功を物語っていると言えるでしょう。
これらの声からも、今回のハッカソンが参加者にとって刺激的で実りある体験となったことが伝わってきます。
謝辞
本ハッカソンの開催にあたり、多大なるご協力を賜りました皆様に、この場を借りて心より感謝申し上げます。
株式会社ハックツ CEO ドリーさんには、ハッカソンのスムーズな運営にご尽力いただきました。 また、AIエバンジェリストの加藤さんには、Difyハンズオンの講師および審査員として、貴重なご知見を共有いただきました。
そして、本ハッカソンを運営した社内運営メンバーの鶴田さん、藤田さん、並びに、事前ワークショップの開催や開発環境の構築など、様々な形で参加者をサポートしてくれた全てのメンバーにも深く感謝いたします。みなさんの支援なくして、このイベントの成功はありませんでした。
まとめ
「Nulab AI Agent Hackathon: Sparking Innovation」は、ヌーラボの全エンジニアがAIエージェント技術と正面から向き合い、限られた時間の中でそれぞれのアイデアを形にしようと奮闘した、まさに熱狂的な一日でした。
このハッカソンで得られた貴重な経験と具体的な成果を活かし、ヌーラボはこれからもAIエージェントと共に、自社のプロダクトと働き方をさらに進化させていきます。